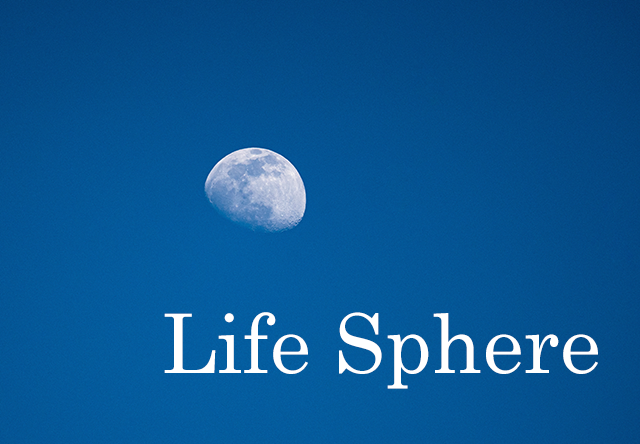先日、大阪大学で脳死患者をドナーとする心臓移植手術が実施された。1997年10月に臓器移植法が施行されて以来、初の脳死患者からの臓器移植だったとのこと。脳死、それを人の死とするかどうか、これはこれまでその現場では大いに議論されてきた問題だが、未だその明確な解答は得られていない。
ところで、私たちの心は何処にあるか、と聞かれて、あなたなら何処を指すだろうか。昔から人が心というとき、これは世界共通で胸に手をあてるようだ。確かに、生命活動上、胸の中にある臓器、つまり心臓はクリティカルな部分だが、それはあくまで血液循環器の中枢であって思考や感覚を司るものではない。モノを思考するのは脳であるなら、心も脳にある、と考えるのが、近代の生物学、そして医学の世界では常識になっている。
ところが、こんな例がある。手術で大量に輸血を受けた患者が、手術前とはまるで別人のような性格に変わってしまったという。その体を流れている血液によって心が左右されるということなのか。とすれば、その血液を循環させている心臓は、その根源といえるのかもしれない。心臓を移植するということは、もしかすると、本当に人の「心」の臓器を移植する、ということにもなるのだろうか。
合理性を重視してきた近代の医療、特に西洋医学においては、人の体の各部位を単なる生体の部品として扱っている。医療の世界だけでなく、一般的にも「心とは何処にあるか?」と聞かれれば、胸に手を当てる人は少なく、頭を指さす人が多数派だろう。であれば、脳が死んだのならば、それが人の死だ、という認識が浸透するのに、今後さほどの年月はかからないだろう。