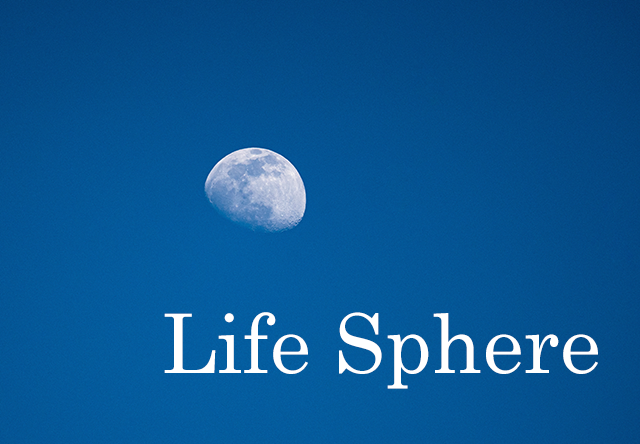科学がそうであるように、医学も完成はされておらず、今もまだ発展途上だ。とはいえ、生理学分野での知識が集積し、医療分野の在り方も、以前とは大きく変わってきている。ただ、病院によってその治療手法もまちまちになっている。例えば「心筋梗塞」の治療方法は、ある病院ではバイパス手術ばかり、またある病院では血栓溶解剤投与ばかりと、病院や医師によって偏りがある。また、それによる治療実績なども、患者側には公開されないというのも問題だろう。
かつて、治療さえ受けられればそれで良かった時代もあった。こうした背景もありこれまで、医療方法そのものについては、さほど問われてこなかったのも現実だ。インフォームドコンセントが叫ばれている今、ようやく患者がその治療方法についても関心を向けられるようになってきたのか。
大学付属病院は、大抵一つの診療科でもいくつかの部屋に分かれている。その名前も第一内科とか第二外科とか、患者から見て実に分かりにくい。消化器内科、呼吸器内科などとそのまま書いてくれれば、患者も自分が何処へ行くべきか分かろうというものなのに。そうなっていのには理由があり、第一、第二などと振ってあるのは、大学の研究室の名前らしいのだ。だからその中身はある時期突然変わることもある。これそのものは問題とは感じられないかもしれないが、現場の管理体制が、患者側本位ではなく、医療側(大学側)本位となっていることは分かるだろう。
また、治療と同時に、その病気の研究なども並行して行われている。これは、今後の医療の為にも必要なことではある。しかし、必要以上に採血したり、下剤を使用してまで便を採取したり、あらゆる点滴(薬剤)が試されたりでは、患者は返って不安になり、治る病気も治らないというもの。
医療の発展のため、今の患者を通過点にするのは必ずしも悪ではない。ただ、最低でも患者にそれを知る権利はある。患者は皆、自分が病気である、というだけで、大きな不安に陥っている。自分がこれから受ける治療はどのようなものであるか、また、実施されている検査にどのような目的があるのか、医療側はそういったことを患者にも伝えるべきなのだ。患者は、それを判断して病院を選ぶこともできる。それこそが「インフォームドコンセント(十分な説明の上での同意)」。
なぜその治療法が適用されるのか。それが最善だからなのか。他にどんな選択肢があるのか。その治療法によるメリットとリスクは何か。そのあたりを、医療側だけでなく、可能な限り患者側にも示していく取り組みというのはあって良いと思う。