これは誰もが思ってはいたけど、あえて指摘してこなかったというか。ロボットが人間の仕事を奪うまで発達するなんて、鉄腕アトムの世界みたいな話がよもや実現する日がこようとは……みたいな非現実的なことが現実になりそうになって顕在化した問題じゃないか。
製造業のロボット化により、景気回復しても雇用が回復しない
(スラッシュドット・ジャパン)
ええ、知ってましたとも。産業用ロボットは同じ繰り返しの単純作業を得意としている。同じ作業を人間がやるのとロボットがやるのとで比較すれば、そりゃロボットの方が誤差も少なくて正確だし、初期導入費とメンテのコストはかかるけど人件費に比べれば安いし、故障はしても修理すればなおるし、病欠とか無断欠勤もない。経営者なら普通に考えてロボットを使うよね。
製造業に限らず、今は様々なインフラがITによって自動化されていて、ライン生産での流れ作業、単純作業に人間の作業員は不要だし、自動販売機やセルフ会計機があればレジ打ち店員も不要だし、コールセンターの自動応答が高機能化して電話受付嬢も不要だし、駅前やデパート、地下街などの案内板だけで案内係も不要だし、自動改札で駅員も不要、無人運転システムで運転手も不要だし……わざわざ人間の手を煩わせず様々なサービスが提供できるようになってとても便利で夢のような世の中になりつつありますよ。
もう人間様は働く必要はない。あとは遊んで寝てれば良い。しかし、困ったことに、人間には労働の義務なんてものが課せられていて、というか、働かないと収入を得られず餓え死にしてしまう。何この矛盾。もうここで何かが破綻しているわけですよ。現状、人間に残された生きる道は、3つ。
- まだロボットにはできない、人間にしかできない仕事をする
- ロボットにもできるけど、まだ人間がやる方が効率が良い仕事をする
- そのロボット自体を開発、製造する仕事をする
1 の候補となり得るのは、まだロボットができない、あるいは不可能とされる何か新しい発想や創造が必要な仕事。例えば、医療や工学諸々、自然科学分野での学術研究とか開発とか。鉱物資源の探索、採掘とか、農林水産業みたいな第一次産業とか。舞台や歌手などエンタメ分野、物書き、絵描き、作曲などのクリエイターの仕事、あとは会社経営とか、新商品開発、そのマーケティング、市場分析あたりか。
ただこれらの仕事も、いずれロボットが取って変わる日が来ないともいい切れない。まさかそんな……と思うかもしれないけど、3、40年前とか万博くらいの年にはその「まさか」と思われていた夢の世界が実現する事態に今なっているわけで。農産物とか今は室内栽培でつくれるようになってきてるし、魚もウナギとかマグロとか養殖ムリと思われてたものも最近できるっぽいし。そうなっちゃえば全部機械で管理できなくもない。芸能分野の仕事でさえ、今わりとロボットにお株を奪われつつある。オリコンランキング上位にVOCALOIDがつける日が来るとか誰が予想したよ?問題解決を考える上では、いずれ全ての仕事がロボットにも可能になるという前提の下で議論していかなくてはなるまい、ということである。
あれです。原発問題。あれは、導入当初に既に様々なリスクが予想されていた。原子炉が制御不能になったりメルトダウンしたりする可能性、使用済み燃料の後始末の問題、廃炉後の施設維持、管理の問題……それらは建前上は織り込み済みだったはずだけど、実際は時代に任せていたというか、その問題が顕在化するような未来には何か優れた解決手段を誰か賢い人が見つけてくれているはずだろうよ…という打算が少なからずあったと思う。ロボットの問題もまさにそれじゃないか。
その意味では 2 も同様。というか、これは 1 よりも早い段階でロボットが人間の領域に侵食してくるはず。ロボットの発達、成長速度をなめたらいかん。今は人手でやった方が良い仕事も、それをより簡単に、より便利にやる機械はあっという間に登場して実用化されるはず。まぁ、そういう方向に技術開発をしているのは人間なのであるが。
ということで 3 である。そう、そのようなロボットをつくっているのは人間なのであって、それこそ人間にしかできない仕事ではないか。今この社会を人間の手間を減らしてより便利なものにしようと、様々な機械やコンピュータ、そのデバイスを開発している産業というのは、これからIT化社会、ロボット化社会において最も成長産業となる分野で、これからはここに人間が入っていけば良いんじゃないか?そういう仕事は今後ますます増えるはず。人の仕事を減らす為の産業で仕事が増える…はず?……あれ?
何か、本末転倒な気がしないでもない。
そもそも、そういうITや工学分野に入る人材のマスって現存の労働者全体に対してそんなに大きなものではないんじゃないか。というより、人材には適不適というものがあって、例えば今、製造業でロボットに仕事を奪われているような人材が技術職に転じて果たしてやっていけるかというと、甚だ疑問である。そう考えると、溢れている人材を成長産業へシフトすることで現状の雇用問題が解決できるとう提言は、どうも幻想な気がしてくる。そもそも、現状ロボットをつくっているのは人間かもしれないけど、それすらもいずれロボットができるようになるとも限らない。ドクターゲロが20号だったとか、リルルが鉄人兵団を呼び寄せるとか。
そうだよ。そのうちロボットが人間より上位の存在になるかもしれない。ロボットがロボット3原則なんかクソ食らえとか言い出したらどうしますか。アシモフもびっくりだよ。
さて困った。もうこれは人間の出る幕が徐々に無くなってくるという予兆なのかも。そんなSFシナリオは手垢がついてしまってるけど、ここにきてわりと現実味を帯びてきてるんじゃないか。だって、現に雇用問題が八方塞がりになりつつあるもんね。で、その大きな原因の1つが、ロボットやITを始めとした
工学の技術革新によるものであることが指摘されているわけだ。
冷静に考えて、今路頭に迷っている労働者たちって、ガチでライン作業員とかその監督とか、いわゆるブルーカラーな人だよね。それってモロにロボットに置換されてるところ(若しくはその候補)なのよね。あと、書類にハンコついて右から左に流す的な事務処理的な仕事もIT化のお陰でWeb上でフロー流せたり、バックも電子処理で済んだりして今までみたいに管理職がわざわざやる必要なくなってる。そういう人たちは、窓際の席からそろそろ窓の外へ、である。
何か、まさに星新一のショートショートとかで皮肉られそうな状況に今なってるんじゃないの?そして、そういうことを大真面目に指摘している経済学者って今日本にいないよね。というか、いたら何か知らんけど干されそうだし。
米国や欧州とかでは、ちゃんと議論されているのかなこれ。ま、専門の学者さんとか、きっと私なんかより賢いでしょうからよくよく考えてそんな可能性はないと判断してるのかもしれないね。或いは逆に、知ってるけど何らかの理由であえて公表してないのか。
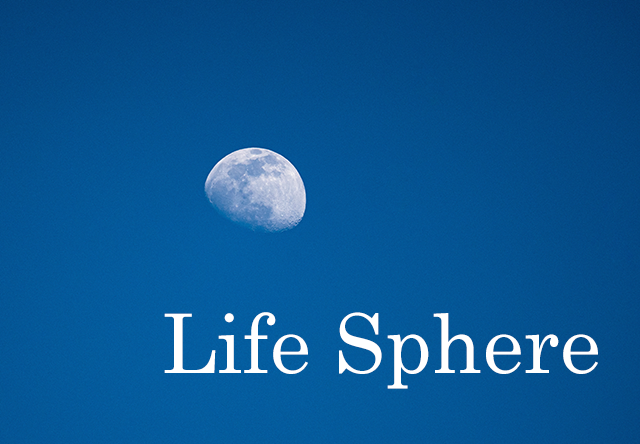


コメント
まったくもってその通り。でも、多分、その系について語ってある本は探せば結構色々ありますぜ。
紫頭怖い顔のおばさん、浜矩子さんなんて、よくそんなようなことを言ってた気がするっす。
でも、異端視されてますよね確かに。(本は面白げなのが多い)
ロボットっていうだけじゃなくて、技術の発展で単純に考えて、ヒト一人あたりが生産できる(こなせる)製品数(仕事量)が、半端無く大きくなってるわけです。
余剰のタスクはダブついて、結局、雇用が失われてしまう。
じゃあ、どうすればよいか!?って答えですが
月影さんはどうおもいます?
あ~。ちょっと前にやってた「C」ってアニメ面白かったなぁ~。
浜ん婆は自分でそういう論文出してるわけじゃないですよね。
これはもう流れに抗わず機械に道を明け渡せばいいじゃないとか思ったりもするけど、何とかして人間の活路を開くとするなら弱者切り捨てでしょう。しかし、そうすると自らが切り捨てられる可能性も肯定することになってしまうから、それはおよそ否定する。そういうところが人間の最大の弱さでしょう。
(…と、何かのRPGのラスボスみたいなセリフをいってみる)