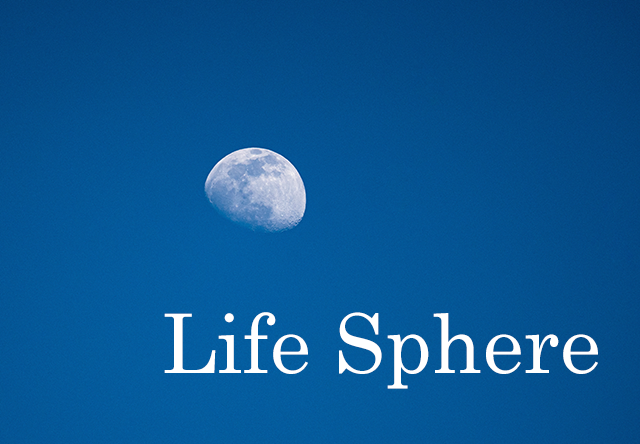「正しい」という言葉には2つの意味があって、ひとつは真実であるということ、本当のことという意味で、もうひとつは善悪でいう善の方であるという意味。後者に関しては人それぞれ考え方や価値観によって違うものだけど、前者は誰にとっても同じ基準で理解できるものであるという概念。
ただ、その“真実”、“本当のこと”とは何かというとこれも突き詰めればそれを見る人によって異なるものであったりする。あくまでそれを認識するのは主観的でしかないから。それでもどうにか万人にとって全く同じ判断材料はないだろうかといったときに重宝されるのは“数学”ということになる。単に数学といった場合、幾何、代数、微分積分と、いろんな分野を含んでいるのだけど、それらに共通しているのは、数値や数式で物事を表現できるという点。
数というのは極めて抽象的な概念で、数を数える対象がミカンだろうとリンゴだろうとメロンだろうと、その個数、数は1、2、3…という数字に統一されてる。数は誰がどうみても変わらない概念であり、絶大な信頼感がある。その数、或いは文字で表される数式は常に同じ規則で、答えを導くことができるのであり、その数式が自然現象を表現するものだと一度証明されれば、その数式の再現性は絶対なので、それを利用して次の真理を求める定理や公理として使われ、あるいはそれを実用に転嫁して生活を便利にすることもできる。
ところで、そうして数式化された“正しい”ことというのは、人の善悪でいう“正しい”ことに必ずしもイコールではない。前者はあくまで判断や技術の材料としての正しさであり、後者は人の利害について判断される正しさである。例えば、核技術は工学的には、即ち限定された範囲の数学的には実用可能な完成されていている真理ではあるのだけど、それはときに人にとって不利益をもたらす可能性も秘めている。
ただ、核技術を使うことによる恩恵は大きく、わずかな材料で膨大なエネルギーを生み出すことができる。反面、それを使うことによるリスクもそれだけ大きい。ここでいいたいのは、核技術そのものは、そのような事実としてあるというだけのものに過ぎないということ。それが恩恵になるか悪害になるかは、それを実用する段になってどう使うのかにかかっているところでもあり、どこまでリスクを許容し、どこから拒絶するかに拠っている。核廃棄物が大量に出たり、事故による放射能のリスクがあったとしてもそれによって得られるエネルギーが必要不可欠ということになるのなら、それは人にとって利益であり、善悪でいえば正しい方へ傾くだろうが、そもそも、正しいとか誤りとかいう判断をそこに入れるべきではない。
そのような技術がある、それに利用価値があるかないかというだけ。これは数学からなる科学技術で支えられる全ての事項にいえることで自動車は交通事故のリスクを常に負っているが必要なら乗るし、コンピュータはあらゆる情報流出を助長しているが必要なら使うし、化学製剤による薬品は自然や生体バランスを崩すが必要なら処方する。
正しいかどうかではなく、使う価値があるかどうかというだけ。道具に罪はなく、使い方に罪があるという見方をさらに転じて使うこと自体にも(リスクがあったとしても)罪があるわけではなく、そのような価値があったから使われたという事実があるだけということ。
人が何かに不安を覚えたり、怒りを感じたりするのもわかるけど、では、その対象が消え失せることでその感情も解決されるのかどうか。自動車が走らなくなれば交通事故は世の中から消えてなくなるけど
その犠牲になる利便性というのもあるだろうということで。