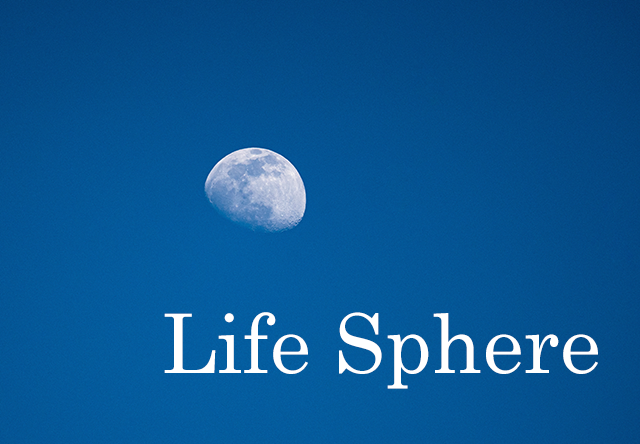うちの実家は禅宗である。宗派でいえば曹洞宗である。
で、地域の曹洞宗のお寺の檀家でもあるので、どういう周期か私は知らないのだが、ときどき坊さん(おそらく住職)が巡回してくる。その坊さんは、家に誰もいなくても、玄関の鍵が開いていれば勝手に上がりこんできて、仏壇の前でお経を読んで、そのまま帰っていく。こんなの都会では考えられないだろう。
私が子供の頃、一人で留守番していたら「ごめんください」と、坊さんが訪ねてきた。こそっと私が顔を出すと、その坊さんは既に草履を脱いで、誰の許可もなしに家にあがろうとしている。そのとき、私はその坊主が何者なのかよく分かっていなかったので、やや、泥棒か?それとも親か誰かの知り合い?などと思いながら、黙って彼の行動を観察していた。
坊さんは仏壇の前に行くと、鐘(お鈴)をちーんと鳴らす。そして、ぼそぼそとお経を唱え始め、節目節目で鐘をちーんと鳴らす。一通り作業を終えると、御札のようなものを取り出して仏壇に供える。いつの間にか、仏壇にはその坊さんに宛ててあると思われる白い包み紙が置かれていて、それを坊さんは懐に収めている。お布施だろうか。とにかく、家の人はこの坊さんが来るということを知っていたらしい、ということを悟り、そこでようやく安心した。そんな記憶がある。今思えば、いわゆる棚経といわれるものだったのだろう。
坊さんの話でもうひとつ。
昔、実家を改築する前は、いわゆる「縁側」というところがあった。その頃は、棚経の坊さんは、玄関からでなく、その縁側からあがってきていたそうだ。で、お経を読み終わると、婆さんがお茶やお菓子を出して労っていた。そのとき、テレビでちょうど高校野球を放送していて、その坊さんはその試合に夢中になってしまったらしい。棚経の最中にも関わらず、結局最後までその試合を見て帰ったとか。
婆さんからは時折そういう昔話を聞くのだけど、そういう何でもない出来事というか、ちょっと昔の日常のような話、しかし今では非日常になってしまった話を聞くのが、何ともいえず心地良かったりする。ちなみに、その坊さんは、今は倉吉の方の寺で住職をしているという。ということは、まだご存命なんですね。
今、街では「鳥取しゃんしゃん祭り」をしている。夜は花火らしい。